今回は、
「在宅医療の現場で感じたメメント・モリの教訓」について書いていきます。
「メメント・モリ(Mémento-Mori)」は、
ラテン語で「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」といった意味を持つ言葉です。
※本記事では「死を想え」に統一して記載します
私は幼少期から死恐怖症でした。
しかし、
身近な人の死と真剣に向き合い、
薬剤師として在宅医療の現場で300名以上の死に触れ、
メメント・モリの教訓を得ました。
一番は、
「死を想い、今を生きる」です。
今回は、
その教訓を共有したいと思います。
・死恐怖症の人
・将来への「ぼんやりとした不安」が拭えない人
必見です。
〈この記事の対象者〉
・FIREやサイドFIREに興味がある人
・労働から解放されたい人
・今より自由に生きたい人
〈注意点〉
筆者の経験と考えを書いていきます。
共通点が多いほど参考になると思います。
〈筆者の特徴〉
30代前半、独身、超倹約家、元社畜、元薬剤師、ゆるいミニマリスト、賃貸暮らし(基本社宅で自己負担小)、負債ゼロ
本記事の目次は下記の通りです。
メメント・モリ:「今ここ」を生き、人生を充実させる思考
以前、
『メメント・モリ:「今ここ」を生き、人生を充実させる思考』という記事を書きました。
※以下、要点を抜粋して記載します
メメント・モリ(死を想え)とは
→「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」という思考
死への「適切な恐怖」により人生が充実する
死はなぜ怖い?「剥奪説」という考え方
→死が悪いものであるのは、死が我々から生の善き点を剥奪するからである
「生まれてきた幸運」と「早死の不運」で相殺
→「生まれてこなかった命」に思いを馳せるのがお勧め
自殺は死をコントロールできる数少ない手段の1つ
→「いつやってくるか分からない」という「過剰な恐怖」に注意が必要
現代で死を想う難しさ:まずは身近なメメント・モリを見る
”身近な死”と真剣に向き合う
仏教の「生死一如」
骸骨・ドクロなど「死」を連想させるモチーフ
Mr.Children「花 -Mémento-Mori-」
〈参考書籍〉
死に対する向き合い方はとても難しいです。
特に平和な現代社会において、
死は「遠い存在」として捉われがちです。
死について何も想わなければ、
人生は平坦でつまらないものになるでしょう。
一方、
死に対して「過剰に恐怖」することも問題です。
全てが馬鹿馬鹿しくなって「ニヒリズム(虚無主義)」に陥ったり、
最悪の場合は自殺を選択することもあります。
メメント・モリは、
「程よい距離感」が大切です。
死への「適切な恐怖」によって、
「今ここ」を充実させて生きることができます。
今回は、
身近な人の死を経験し、
薬剤師として在宅医療の現場で300名以上の死に触れて得たメメント・モリの教訓を共有したいと思います。
在宅医療の現場で感じたメメント・モリの教訓
在宅医療の現場で感じたメメント・モリの教訓について、
身近な人の死を含めて3つの話を挙げて解説していきます。
「植物状態」で5年間生き延びた祖父
小学生の時に亡くした祖父は、
「植物状態」で5年間生き延び、
亡くなりました。
不慮の事故により頭部を強打したことが原因です。
この死は、
まるで「生」と「死」の境界線を見ているようであり、
死恐怖症の私にとって苦痛以外の何物でもありませんでした。
病院へお見舞いへ行き、
おばあちゃんやお母さんが、
植物状態になったおじいちゃんに話しかけます。
しかし、
全く応答がありません。
どうやら、
意識もないようです。
※諸説ありますが
問いかけに対する応答も一切なく、
管に繋がれて「なんとか生かされている」その姿を見て、
まるで「生きている意味がない」ように思え、
「生」と「死」について考えさせられました。
お見舞いのたびに気分が落ち込み、
憂鬱な気分になるし、
正直「時間の無駄」としか思えませんでした。
人間性を疑われても仕方ありませんが、
死恐怖症の子供には本当に耐えがたい時間でした。
おばあちゃんやお母さんが、
植物状態になったおじいちゃんに話しかける「それ」にまるで意味を見い出せません。
正直なところ、
遺影や遺骨に話しかけるそれと同じくらい、
ぬいぐるみに話しかけるそれと同じくらい、
無意味で虚しい行為だと思っていました。
例え意識があったとしても、
正確に伝わらず、
それに対するレスポンスがないのであれば、
まるで意味がなく、
虚しく切ないものです。
この「変わり果てた姿」は、
果たして「大好きなおじいちゃん」の同一なのか?と、
悶々と思考する日々でした。
※のちに、「同一性の問題」「テセウスの船」という概念を知ります
当時は目を背け続けていたため教訓を得るのに時間がかかりましたが、
「命を長らえること」と「生きること」は必ずしも同じではないと、
”有意義に生きる時間はあまりにも短い”ことを痛感しました。
一番身近な母親の死
大学生の時に亡くした母は、
15年間にも及ぶがん闘病ののち、
亡くなりました。
しかし、
私が”母が癌である”と言う事実を知ったのは、
母が「余命半年」を宣告された時でした。
子供である私たち姉弟に対してはずっと隠し通されており、
なかなか奇妙な体験でした。
※この件に関しては、下記記事で詳しく解説しています
後から思い返せば、
その事実に気づくチャンスはいくらでもあり、
違和感※はたくさんあり、
気づかない方がおかしい状況でしたが、
私は全く気づくことができませんでした。
※違和感の例
・夜中にかつらを外す姿を見てしまった(抗がん剤の副作用のため)
・抱っこを求めてもやんわりと拒否され、スキンシップが無かった(乳がんで切除していたため)
・母親が一人で出掛けて、代わりに親戚の叔母さんが家に来る日が定期的にあった(定期受診しなければならないため) など
「違和感の正体を知りたくない」
という気持ちもあったのだと思います。
まんまと洗脳されていたのです。
その後、
母は半年持たずして亡くなってしまいました。
未熟だった私は「真実を隠し続けてきた親族を恨む」という愚行を行い、
その時にしかできない事が山ほどあったのにも関わらず、
ろくに親孝行が出来ませんでした。
最後の最後まで、
感謝の気持ちなどを素直に伝える事が出来ず、
母が居なくなってから、
『もう伝えれない』という事実が、
とてもつらい後悔を生みました。
今しか出来ないこと、
この人が存在するうちにしか伝えることが出来ないこと、
そんな当たり前のことが世の中に溢れています。
痛い代償を払い、
「今を生きる」重要性を学びました。
在宅医療で触れた300名以上の死
在宅医療の現場、
とりわけ緩和ケアの領域に携われば、
死は決して遠い存在ではなく、
すぐそばにあるものだと痛感させられます。
薬剤師は医療従事者の中で”最も死から遠い存在”と言っても過言ではありませんが、
私は敢えて緩和ケアの領域に携わり、
300名以上の死に触れました。
そして、
出来る限り真剣に向き合うため、
積極的に対話を行いました。
その多くは癌患者で、
そのほか心疾患や老衰、
パーキンソン病やALSなどの難病患者にも関わりました。
その中で感じたことを綴っていきます。
死の受容の中にある「後悔」
私が触れた死の多くは、
あらゆる治療を行ったがその甲斐なく在宅医療に移行し、
余命宣告がされているような「終末期」と呼ばれる患者様でした。
「最期は家で過ごしたい」という背景があるため、
ほとんどの患者様の最期は穏やかなもので、
「キューブラー・ロスの死への5段階※」における「受容」の境地に足を踏み込んでいました。
※人間が死と向き合う時の心理変化として、下記5段階を踏むと言われている
1.否認
自分の命が長くないことに衝撃を受け、その事実を感情的に否認したり、
その事実から逃避しようとしている段階。
周囲の認識や態度にギャップが生じるため、孤立しがちになる。
2.怒り
死ぬという事実は認識したが、
一方で、「ではなぜ、自分がこのような境遇になってしまうのか」といった思いが強く、
周囲に反発したり、怒りがこみあげてきたりする。
3.取り引き
死をもう少し先延ばしできないか、
あるいは、奇跡が起こって死を回避できないかと考えて、
神仏にすがったり、善行を行ったりする。
4.抑うつ
死を避けられないことが分かり、
あきらめや悲観、むなしさ、憂うつ、絶望といった気持ちが支配して、落ち込む。
5.受容
死を、誰にでも訪れる自然なものとして受け入れるようになる。
これまでの価値観や視野とは異なる次元があることを理解し、心静かに暮らす。
しかし、
穏やかといえど、
”後悔の念”は何度も耳にしました。
「もっとチャレンジすればよかった」
「もっと自由に生きればよかった」
「大切な人ともっと時間を過ごせばよかった」
若い私に託すような、
そんなメッセージを多数受け取りました。
下記書籍にも、
死ぬときの後悔No.1は、
「もっと冒険しておけば良かった」だと書かれています。
患者様に託されたメッセージを大切にし、
「後悔を残さぬよう出来る限り冒険しよう」と考えた結果、
FIREという選択肢が大きくなりました。
進化学的には「いつ死んでもおかしくない」
癌も心疾患も難病(パーキンソン病やALS)も、
理不尽だと感じることは多々ありました。
※タバコによる肺癌は除く
日々懸命に生きてきた善人が病に苦しみ、今すぐ死ぬべき詐欺師がのうのうと生き続ける理不尽がそれを加速させます。
なぜこの理不尽が起こるのかを科学的に勉強したところ、
「進化学」においてその答えが出ていました。
進化学の観点から見ると、
生物は基本的に「生殖(子孫を残すこと)」を最優先に進化しており、
生殖が終わった後に発症する病気(例えば癌、心疾患、アルツハイマー病など)は、
子孫を残す能力には影響しないため、
自然選択の影響を受けにくくなるということです。
その結果、
これらの病気の遺伝的要因は淘汰されることなく蓄積し、
次世代にも受け継がれます。
癌も心疾患も難病(パーキンソン病やALS)も、
中年以降に発症する病のほとんどは淘汰されることなく、
進化学的には「いつ死んでもおかしくない」ということです。
まだ30代前半ではありますが、
この手の疾患にはいつ罹ってもおかしくありません。
そうなれば、
「明日死んでも大丈夫」という気概で、
後悔なく日々を懸命に生きる必要があります。
「最後の足跡」を考える
在宅医療の現場は、
「他人のテリトリーに踏み込む」というなかなか特殊な現場だったと思います。
それは物理的なテリトリーだけでなく、
精神的なテリトリーの方に大きな比重があります。
”医療情報”という最もセンシティブな領域で関わり、
「死をも共有する」という、
精神的なテリトリーに踏み込む貴重な経験でした。
そして、
医療従事者としての役目が終われば、
物理的なテリトリー(患者様の家)にも、
精神的なテリトリー(患者様の心)にも、
二度と立ち入ることはありません。
切ない「最後の足跡」をつけ続ける日々でした。
「最後の足跡」とは、
「その場所に最後に踏み込む一歩」という意味です(私の造語)。
※物理的な「最後の足跡」については、下記記事で詳しく解説しています
「最後の足跡」を考えるとき、
ギュッと切ない気持ちになったり、
シャキッと引き締まる気持ちになったりします。
日々の「足跡」の中には、
「最後の足跡」となるものも混じり込んでいます。
物理的なテリトリーであっても、
精神的なテリトリーであっても、
予期せぬ形で突如「最後の足跡」になる可能性があります。
「最後の足跡」のなりうる一歩一歩を大切にすることを学びました。
まとめ:「今この瞬間をどう生きるか」を考えさせてくれる大切な教え
以上、
「在宅医療の現場で感じたメメント・モリの教訓」についてでした。
まとめです。
ーーーーーーーーーー
メメント・モリ:「今ここ」を生き、人生を充実させる思考
→死への「適切な恐怖」で「今ここ」を生きること
在宅医療の現場で感じたメメント・モリの教訓
①「植物状態」で5年間生き延びた祖父
→有意義に生きる時間はあまりにも短い
②一番身近な母親の死
→この人が存在するうちにしか伝えることが出来ないこと
③在宅医療で触れた300名以上の死
・死の受容の中にある「後悔」
・進化学的には「いつ死んでもおかしくない」
・「最後の足跡」を考える
ーーーーーーーーーー
死を想うこと、
メメント・モリは、
「今この瞬間をどう生きるか」を考えさせてくれる大切な教えです。
死を意識することは、
より良く生きるための道しるべとなります。
だからこそ、
「死」を遠ざけるのではなく、
時折立ち止まって考えてみることが大切です。
また、
ここで誰もが直面するのが、
「今を楽しむべきか、それとも将来に備えるべきか」という問題だと思います。
・好きなことをやりながら生きるのが理想
・でも、将来のために備えておかないと不安
・かといって、今を犠牲にしすぎると後悔するかもしれない
このバランスをどう取るかは、
人それぞれの価値観に委ねられるでしょう。
しかし、
「いつ死んでも後悔しない生き方」 を基準に考えれば、
自然と各々の人生の答えは見えてくると思います。
今日一日を振り返ったとき、
「悔いなく生きられた」と思えるでしょうか。
もし少しでも迷いがあるなら、
今この瞬間から、
自分の人生をより豊かにする一歩を踏み出して欲しいと思います。
私は多くの死に触れ、
死と真剣に向き合った結果、
一旦FIREすることにしました。
次回の記事で、
「FIREを決意した理由:死を意識して気づいた「時間の価値」と後悔しない生き方」についてまとめていきます。
↓こちらもおすすめ↓
・貧乏ごっこの概要
・お金の後悔シリーズ
・ゆるいポイ活
・サイドFIREの概要
・サイドFIREの達成戦略
・9年で4,000万円作った過程
・サイドFIREの葛藤
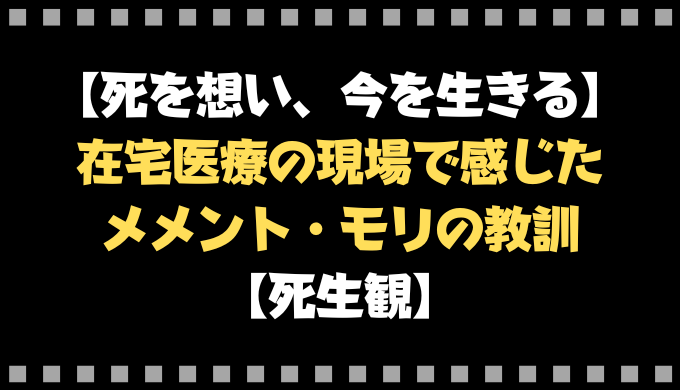
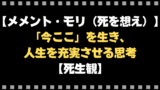


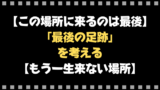

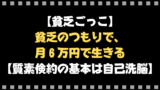
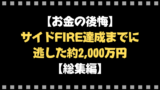

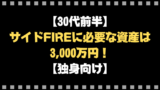
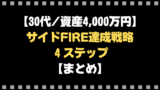
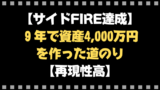
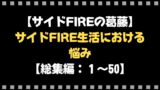
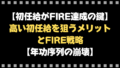

コメント